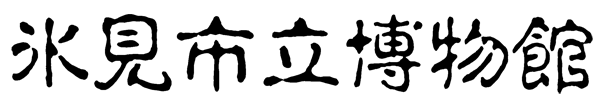今年度の特別展
今年度の特別展
特別展「ひみのたからもの」―能登半島地震と文化財レスキュー
令和7年10月17日(金)~11月9日(日)
そうしたなか、発災直後から氷見市立博物館が取り組んだのが文化財レスキューです。文化財レスキューとは、被災し、著しい劣化が危惧される文化財を安全な場所に移し、必要であれば応急処置等を実施する作業です。対象となる文化財は、地域で大切に守り伝えるべき有形文化財(美術工芸品、古文書、古写真、考古資料など)および有形民俗文化財(生活用具、農具、漁具、信仰用具、職人の道具類など)を指し、指定文化財はもちろん指定を受けていない文化財も含みます。
氷見市では、氷見市立博物館が中心となって文化財レスキューを実施、1月以来、件数にして40件超、数千点におよぶ文化財を被災建物よりレスキューし、資料の受け入れを行ってきました。なかには、今年終戦から80年を迎える太平洋戦争に関する資料や、古文書、古いアルバム、その他氷見の歴史やくらしに関するものが多く含まれています。
被災地における文化財レスキューは、それら貴重な文化財を守り、後世に伝えていくために欠かすことのできない取り組みです。文化財レスキューによって寄せられた資料は、まさにこの地域の歴史を知るうえでかけがえのない「たからもの」であるといえるでしょう。
本特別展では、令和6年1月1日以降実施してきた文化財レスキューの取り組みのなかで、当館がレスキューし市民の皆様から寄贈・寄託されたさまざまな資料を紹介します。被災を乗り越えレスキューされた資料の数々を通じて、あらためて地域の歴史に思いをはせていただければ幸いです。
 おしらせ
おしらせ
氷見市文化財センター一般公開のお知らせ

当館は「氷見及び周辺地域の漁撈用具」として国の登録有形民俗文化財となっている富山湾一帯から能登半島の和船を中心に、多数の和船を収蔵展示しています。そのほか、農具や生活用具など様々な民具も収蔵展示しており、公開日には学芸員が随時解説します。
場所:氷見市文化財センター
(氷見市中田645番地:旧女良小学校)
※申込み不要、入場無料
【令和7年度 氷見市文化財センター開館日について】
開館時間:午前9時~午後4時
4月26日(土)、5月24日(土)、6月28日(土)、
7月26日(土)、8月23日(土)、9月27日(土)、
10月25日(土)、11月22日(土)、3月28日(土)
【文化財レスキュー】令和6年能登半島地震に伴う文化財レスキューのお知らせ
被災した家屋や蔵などに古文書や民具など氷見市の歴史を知るうえで大事な資料が残されている可能性があります。もしそうしたものがありましたら氷見市立博物館までご一報ください。ささいな情報でも大丈夫です。地域の歴史を未来に残すためにも、よろしくお願いいたします。
※文化財レスキューとは
文化財レスキューの対象となる文化財は、地域で大切に守り伝えるべき有形文化財(美術工芸品、古文書、古写真等の動産文化財)および有形民俗文化財(生活用具、農具、漁具、信仰用具、職人の道具類などいわゆる民具)を指し、指定文化財はもちろん指定を受けていない文化財も含みます。文化財レスキューとは、被災し、著しい劣化が危惧される文化財を安全な場所に移し、必要であれば応急処置等を実施する作業です。
氷見市では、氷見市立博物館が中心となって文化財レスキューを実施し、資料の受け入れや保管を行う予定です。
【問い合わせ先】
(1)電 話 番 号 0766-74-8231
(2)メールアドレス hakubutsukan@city.himi.lg.jp
氷見市「孫とおでかけ支援事業」に参加しています!

氷見市立博物館に、お孫さんとおじいちゃんやおばあちゃんが一緒に入館する場合は、入館料が無料になります。
お孫さんと氷見を発見する楽しいひとときをお過ごしください。
※祖父母の居住地は富山県内の方が対象です。
※お孫さんの年齢・居住地は問いません。
※平成28年4月29日(金)より実施。
 常設展案内
常設展案内
| 2014.12.12 | 常設展示室に吉田初三郎「氷見市景勝鳥瞰図」を展示しました。 | |
| 2010. 6. 4 | 常設展示室に「木造和船の建造技術」のコーナーを新設しました。 | |
| 2009. 1. 6 | 常設展示室に中世石造物のコーナーを新設しました。 | |
| 2007. 4. 1 | 常設展示室に「昭和30年代コーナー」を新設しました。 |