|
|
|
 |
|
博物館では、開館以来多数の漁撈用具の収集・展示を行ってきましたが、近年は、特に木造和船とその建造技術の調査・研究に力を入れています。
今回、その成果の一部として「木造和船の建造技術」コーナーを新設しました。
ここでは、テンマと呼ばれる小型の和船の建造過程を10分の1スケールで再現した模型のほか、かつて氷見市内で造船業を営んでいた船大工の方々から寄贈していただいた船大工用具を展示しています。
|
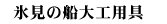 |
| 氷見では、昭和40年代頃まで木造の和船が建造されていました。和船の建造が盛んだった当時、船に用いられる木材は市内の山林から切り出されました。かつては専業の木挽きが丸太から板材に製材していましたが、後には木挽きの数が少なくなったこともあって、船大工自らが製材を行うようになりました。丸太を板に挽[]くには、マエビキという木挽き用の大きな鋸[]が使用されました。 |

|
|
船材の加工には、粗削[]り用にマサカリやチョウノといった斧[]が用いられたほか、横挽[]きのガンド、縦挽[]きのガガリ、穴をあける際に使うヒキマワシなど、各種の鋸[]が使用されました。また、船大工独特の作業である「アイバスリ」という板と板との接合面のすり合わせにも専用の鋸が用いられました。使われる鋸はアイバノコといい、目の細かさによって粗目[]のオオノコ、中目[]のチュウバ、仕上げ用のコブクラの3種がありました。
氷見の造船で使用された船釘[]は、大きく4種類に分けられます。板と板を縫い合わせるオトシ、カイバタなどを固着するためのカイオリ、ハタとチョウを接合するためのマガシラの3種類が一般的に用いられました。また、ドブネやテントといった大型船のオモキとチョウを接合するためには、マガシラに替えてホーズキという釘が使用されました。こうした4種の船釘は、船の大きさに合わせて様々な寸法のものが用意されていました。
そのほか、角度、長さの測定や墨付けに用いる墨壺[]、マガリガネ(曲尺)、ジユウガネ、スイヘイ(水準器)、スミサシといった墨掛[]け道具、船釘を打つ前の下穴をあける3種のツバノミ、用途に合わせた複数のカンナ類、多様な幅の角ノミや丸ノミ、突[]きノミなどの道具が使用されました。これらは、たいてい自作の道具箱に収められました。
常設展示室に展示している船大工用具は、氷見で和船の建造を手掛けた船大工の方々から寄贈を受けたもので、十二町潟[]で使われた川舟、タズル(ズッタ)の建造に用いられた道具を中心に構成しています。
|
|
|
 |
|
 |
氷見市立博物館 〒935-0016 富山県氷見市本町4-9 TEL : 0766-74-8231 /
FAX : 0766-30-7188 / E-mail : hakubutsukan@city.himi.lg.jp
|
|
|