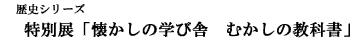 |
幕末期以降、氷見町の商家の主人らが先生役の師匠となり、また町まで距離があり通うことが難しい山間の村々では、地元の僧侶らが師匠となって、寺子屋が開かれました。町人や農漁民の子弟は、寺子屋に通い、「往来物」を中心とした手習いや素読、算盤など、社会生活を営む上で必要な知識と技術を身に付けました。
明治5年、明治政府は近代学校制度に関する基本法令である「学制」を発布し、氷見地域では翌明治6年から順次小学校が開校されて、明治10年には35校1分校を数えました。その後の社会情勢や、教育環境の変化により、新設や統合を経て現在は12校となっています。
各校の約140年間の歩みは、沿革史や記念誌等で詳しく伝えられ、さらに家庭に残る卒業写真や行事写真等からは、校舎の変遷や学校生活の一端をかいま見ることもできます。
また、小学校で利用された教科書も幾多の変遷をたどります。文明開化の流れを受けた欧米の翻訳教科書から、文部省による検定教科書へ、そして明治36年からの五期にわたる国定教科書へと次第に国家主導の色合いを濃くしていきました。さらに、昭和20年代の墨塗り教科書から、戦後の検定教科書に移り変わり現代へと繋がります。
この特別展では、実物の教科書のほか、教室内で用いられた掛け図や地球儀などの教材を中心に、氷見地域の教育内容の移り変わりを概観します。また、着物や履物、弁当箱など児童の身の回りの品々を展示することにより、昔の子どもたちの学校生活の実際についても紹介します。
|



|
展示構成
・小学校の変遷(木造校舎の写真)
・写真に見る学校行事
(運動会、学芸会、臨海学校等)
・教科書(往来物、明治期検定教科書、国定教科書、
墨塗り教科書、戦後の教科書)
・掛け図(単語図、修身掛図、明治30年代の富山県地図)、
地球儀等の社会科教材
・児童らの身の回りの品々
(着物、マント、履物、カバン、石板、筆)
・昔の教室の再現(二人掛け机、木製椅子)
・体験コーナー(石盤体験)など
|
| 会 場 |
氷見市立博物館特別展示室 |
| 会 期 |
平成25年3月1日(金)から3月24日(日)まで |
| 休館日 |
月曜日。3/20(春分の日)は開館。 |
| 時 間 |
午前9時から午後5時まで |
| 観覧料 |
無料 |
| 行 事 |
【資料解説会】
日時 : 平成25年3月2日(土) 午後2時〜3時
会場 : 氷見市立博物館特別展示室
【図書コーナー】
図書館との連携事業のひとつとして、会期中特別展テーマに関する
図書コーナーを閲覧室に開設。 |
| 図 録 |
 |
『特別展 懐かしの学び舎 むかしの教科書』
H25年3月発行、A4判 42p、400円。
(本文:モノクロ38p、カラー図版4p) |
|
|
|HOME|過去の特別展示一覧|今年度の特別展示|常設展示|図録の通信販売| |
