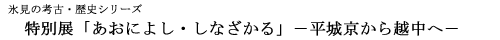 |
8世紀、奈良時代の中頃、氷見市南部の十二町潟に舟を浮かべて遊んだ人たちがいました。時の越中国守大伴家持の一行です。その時の様子は、万葉集に残された多くの歌から偲ぶことができますが、では実際に家持が見た世界とはどのようなものだったのでしょうか。
奈良時代は、陸の交通が国家の政策として重視された時代です。平城京を中心に幅の広い直線の道路が整備され、決まった間隔ごとに駅家が設けられ、中央と地方の情報伝達や物資の輸送が管理されたと思われます。
近年、富山県・石川県では古代北陸道と推定される道路遺構が、発掘調査によっていくつか確認されています。また、奈良時代の遺跡の発掘調査が増え、当時の生活の様子が少しずつ解明されつつあります。
この特別展では、こうした奈良時代の世界を、平城宮と越中、さらにはそれをつなぐ北陸道沿いの遺跡の代表的な資料によって紹介しました。 |


「あおによし・しなざかる」展示風景
|
| 会 場 |
氷見市立博物館特別展示室 |
| 会 期 |
平成10年10月23日(金)から11月15日(日)まで |
| 観覧料 |
無料。ただし、解説図録を実費販売。 |
| 図 録 |
 |
『特別展 あおによし・しなざかる』
H10年10月発行、B5判、28p、200円。
(表紙:モノクロ、本文:モノクロ、カラー図版1p) |
|
|
|HOME|過去の特別展示一覧|今年度の特別展示|常設展示|図録の通信販売| |
