|
|
|
 |
|
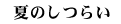 |
|
常設展示室の「氷見の民家」では、季節ごとにしつらいを変えています。
夏には、蚊帳を吊り、すだれを掛けたしつらいになっています。 |
■蚊帳
仏壇のある奥座敷に対して、前座敷にあたるデイと呼ばれる部屋には、蚊帳を吊っています。
蚊帳は、夏の夜に蚊にわずらわされずに涼しく安眠するための夜具です。四隅につけた吊手で吊ります。蚊帳の歴史は古く、奈良時代の文献にも登場しますが、庶民に普及するのは江戸時代になってからです。
上等品の材料には、絽[]や紗[]などの絹織物も一部用いられましたが、一般には麻糸を織ってつくられた麻蚊帳が広く使われました。とりわけ麻は吸湿性にすぐれ、余分な湿気を吸い取ってくれるため、暑くて寝苦しい晩でも蚊帳の中は幾分ひんやり感じて寝やすかった、といいます。
色も、黄色がかった緑色の萌黄[]に縁布[]が暗い赤色の茜[]色の鮮やかな色のもののほか、生成りや薄い水色の浅黄[]、二色のぼかしなどがみられます。なかでも、萌黄色の蚊帳は「青蚊帳[]
」とも俗称されました。
一方、蚊帳はまた大変高価なものでした。昭和30年代初め頃、6畳間に吊る本麻製の蚊帳は1張り4,500円余り、昭和50年代半ば頃の小売り価格は、同じく1張り2万数千円ほどでした。
特に町方の裕福な家では、家人が使う蚊帳とは別に来客用の蚊帳を幾張りも用意してあり、普段は露地[]奥に建つ道具蔵の長持[]の中に納めておき、来客のある時に取り出して使われました。
■すだれ
オイ(広間)の縁側にはすだれを掛けています。
割竹や細い葦[]を編んでつくられたすだれは、夏の強い日差しを防ぐため軒[]や縁先[]に掛けられました。
また、すだれを掛けると明るい戸外から暗い室内への見透[]かしを遮[]ってくれることから、夏の間風通しを良くするため室内の戸障子[]を取り払って開け放たれた部屋の目隠し用に重宝[]がられました。
■蚊遣り豚
蚊帳よりももっと手頃な蚊除けの道具として、蚊取り線香と蚊遣[]り豚があります。
除虫菊[]の粉末と杉粉とを練り合わせて渦巻状につくった蚊取り線香と、前後に穴を開けた豚を型取った素焼きの蚊遣り豚は、明治末年頃から使われるようになったとされ、それ以前は松や杉、カヤの葉や、干したヨモギをいぶすことによって蚊を寄せ付けないようにしていました。
密閉された部屋に設置されるエアコンや網戸が広く普及するほんの少し前まで、蚊帳や蚊遣り豚のほか、すだれや団扇[]などは、湿度が高く蒸し暑い夏を少しでも快適に過ごすための道具としてなくてはならないものでした。
また、軒先に風鈴を吊るしてその音色を楽しんだり、縁先に打水[]をして一時の涼を取るほか、陶製の湯呑[]みをガラス製のコップに変えるなどして、少し以前の人たちは身近なものを上手に使い回しをして、季節感を楽しんでいたようです。 |



 |
|
 |
|
 |
氷見市立博物館 〒935-0016 富山県氷見市本町4-9 TEL : 0766-74-8231 /
FAX : 0766-30-7188 / E-mail : hakubutsukan@city.himi.lg.jp
|
|
|