 |

ドブネの船首部分
|
日本海側特有の大型の漁船で、胴部分の断面が四角形のところから、能登内浦地域では「箱船」ともよばれた。全長は大きなもので14〜15m余りもあり、シキ(船底部分)には幅30cm、厚さ15cm余りの部厚いスギ材を横に繋いでつくられている。
大型のドブネだと、1艘に水揚げされたブリを900〜1000匹も積んだといい、江戸時代にはおもに藁縄を編んでつくられた台網[](鰤網)の網取り(網起こし)に使われた。
丈夫で長期間の使用に耐えたが、「ドブネ1パイ、家1軒」といわれるほど建造費が高く、また船足(速力)が遅いため廃れ、昭和40年代に入ると次第に使われなくなった。
操船は、トモ櫓[]1丁にワキ櫓[]2丁のほか櫂[]8〜10丁余りを使い、ドブネ1艘には十数人の漁師等が乗り込んだ。
|
|
 |

カンコ (長さ:5.80m、幅:1.48m、高さ:0.51m)
採集地:富山県氷見市北大町地内
製作年:昭和10年7月
|
平底のため船足はあまり速くはないが、比較的丈夫で割合長期間使用できた。櫓[]と櫂[]で操船し、長さ8〜9mの大型のカンコはおもに春先にマイワシやマイカを水揚げする春網(鰯網)の網取り船のほか、地曳網の網船などにも用いられた。
長さ5〜6mのやや小型のカンコは、手繰[]り網や刺網[]、延縄[]漁などの個人操業をする小商売の漁師たちに重宝がられた。また、蔵町カンコとよばれた比較的大型でエンジンを搭載したカンコ型動力船は、能登通いなどの荷船や、大敷網[]に用いる網錘[]りにする砂利の運搬などに使われた。
|
|
 |

テンマ (長さ:4.43m、幅:1.39m、高さ:0.45m)
採集地:富山県氷見市中波地内
製作年:昭和41年
|
昭和40年代以降、ドブネに代わっておもに大敷網の網取りに用いられたテントと同様に、三枚合わせの底板の両側にハタイタ(舷側板)を立てた五枚仕立ての構造をもつ。
テントよりずっと小型のため、定置網の網取りには使われず、軽くて扱い易いといって一本釣りやタコツボ漁のほか、サザエやワカメ・テングサ・エゴノリなどを採集する磯見漁等に用いられた。
たいてい小商売の漁師が1人乗り、櫓と櫂を練って操船された。漁の最中は、1人で櫂を練りながら箱眼鏡で海底の獲物を採集するため、人によってはマネキ櫂という小型の櫂を足で練る人もいた。
|
|
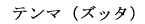 |

テンマ(ズッタ) (長さ:3.68m、幅:0.88m、高さ:0.34m)
採集地:富山県氷見市十二町
製作年:昭和30年代頃
|
かつて十二町潟近辺ではズッタと呼ばれる平底の潟舟・川舟が用いられた。
小型のものはテンマと称し、2枚合わせの船首部を除き、4枚の底板の両側にカイバタ(舷側板)を各1枚ずつ立ててつくられた。材料の多くはスギが用いられ、組合わせ部分は鉄製の船釘で留めたうえ埋木が施される。
通常櫓と櫂は用いず、竹竿で操船された。潟や川での荷船のほか、十二町潟ではハダコ田などの深田への行き来や農作業に使われた。
|
|