氷見市液状化対策推進事業について
液状化現象について
液状化とは
液状化とは、地震が発生して地盤が強い衝撃を受けると、今まで互いに接して支えあっていた土の粒子がバラバラになり、地盤全体がドロドロの液体のような状態になる現象のことをいいます。液状化が発生すると、地盤から水が噴き出したり、また、それまで安定していた地盤が急に柔らかくなるため、その上に立っていた建物が沈んだり(傾いたり)、地中に埋まっていたマンホールや埋設管が浮かんできたり、地面全体が低い方へ流れ出すといった現象が発生します。

液状化により起きる被害
液状化がおこると、次のような被害が発生します。
1. 地盤の支持力が低下することにより発生する、建物等の沈下や傾斜
2. 噴砂(水と砂が地中から噴き上げてくる現象)などによる被害
3. 地下に埋設された水道管・ガス管・電線の損傷による、ライフラインの寸断
地区全体での対策【道路と宅地の一体的な液状化対策】
宅地液状化防止事業 ※国補助事業
主に宅地の用に供され、大地震時等に液状化現象が発生する可能性のあるまとまった地域において、災害の発生(液状化現象など)を抑制するため、道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策を推進する事業です。
事業要件
1. 当該宅地の液状化により、公共施設(道路、公園、下水道、河川、水路その他公共の用に 供する施設をいう。)に被害が発生するおそれのあるもの
2. 変動予測調査等により、液状化による顕著な被害の可能性が高いと判定された3,000平方メートル以上 の一団の土地の区域でありかつ、区域内の家屋が10戸以上であるもの
3. 公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われていると認められるもの
主な対策工法
地下水位低下工法

地下水低下工法(イメージ)
住宅地や道路部分の地下水位の高さを強制的に低下させて液状化による被害 を軽減させたり、地表面下の数メートルを非液状化層とすることにより、液状化が発生する可能性を 軽減し、液状化の被害を抑制する工法
格子状地中壁工法

格子状地中壁工法(イメージ)
セメントなどの改良材を地中に供給し、原地盤の軟弱土と改 良材を強制的に混合撹拌することで、地中に柱列状の固化壁を造成し、これらを格子 状に配置し液状化地盤を囲い込むことで、地盤のせん断変形を抑止し液状化を抑制する工法
氷見市液状化対策検討委員会
令和6年能登半島地震により液状化被害を受けた地区における被害状況の調査分析、液状化対策事業計画の策定及び液状化対策事業の実施にあたり、その安全性、経済性等の妥当性について地盤の液状化に関する専門家等の意見を反映させるために設置されたものです。
詳細については、下記リンクをご覧ください
住民説明会

検討委員会において、専門的(学術的)見地等から、液状化対策の対象範囲に設定した3地区において、開催したものです。
詳細については、下記リンクをご覧ください。

検討委員会で選定された対象範囲
個人での対策【宅地の液状化対策】
宅地液状化等復旧支援事業費補助金
令和6年能登半島地震により液状化被害を受けた地域において、住宅の用に供されていた宅地の復旧や地盤改良、住宅基礎の傾斜修復を支援するものです
対策工事

1.擁壁、地盤の原型復旧工事
2.液状化の再度災害防止のための地盤改良工事
3.住宅基礎の沈下又は傾斜を修復する工事
(ジャッキアップなど)
詳細については、下記リンクをご覧ください。
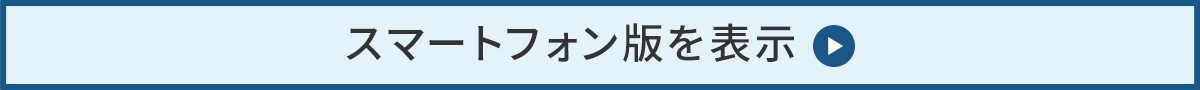








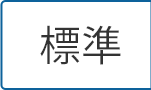




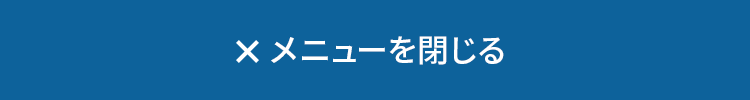
更新日:2025年08月12日