氷見市の概要
位置・地勢・人口
私たちの住む氷見市(ひみし)は、富山県の西北、能登半島の東側付け根部分に位置しています。
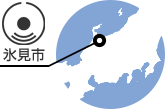
多くの幸をもたらしてくれる「青い海」と「みどり豊かな大地」を有し、人の心を引きつける自然の恵みに包まれています。
日本海側有数の氷見漁港には、四季を通じて156種類もの魚が水揚げされ、初夏の「マグロ」、冬の「寒ブリ」、そして「氷見いわし」は広辞苑にも掲載されるほど有名です。
また、日本ではじめて発見された洞窟住居跡「大境洞窟」や万葉の歌人大伴家持ゆかりの史跡など、歴史のロマンにも満ちあふれています。
さらに、近年は市内各地で温泉が湧出し「能登半島国定公園・氷見温泉郷」の名称でPRに努めています。

位置
経緯度:東経136度59分 北緯 36度51分
面積
230.54平方キロメートル
- 東西18.25キロメートル 南北21.65キロメートル
- 海岸線延長19.5キロメートル
人口・世帯
氷見市民憲章
~みんなでつくる わたしたちのまち ~
はるかに立山連峰を望む氷見市は、海から里山まで広がる豊かな自然に恵まれています。また、先人の知恵に学びながら、様々な歴史や文化を育んできました。
この美しいふるさとに愛着と誇りをもち、さらに市民が主役となってまちづくりを進めることを目指し、ここに市民憲章を定めます。
第1章 自然と調和したまち
海と大地の恵みに感謝し 豊かで美しい自然を守ります
第2章 笑顔あふれるまち
温かい家庭や地域の中で 健やかな心と体を育みます
第3章 安全安心なまち
信頼のきずなで支え合い 心豊かに暮らせるまちを築きます
第4章 市民が協働するまち
市民一人一人が自分のよさを生かし まちづくりに参加します
第5章 活力ある交流のまち
人も心も通い合う にぎわいと活気に満ちたまちをつくります
主な産業
- 農業
- 漁業
地名の由来
「氷見」と書いて「ひみ」読ませるのは全国的にも珍しく、愛媛県西条市に同じ読み方をする町名がありますが、その他には無いものと思います。もし有りましたら是非教えてください。由来については、諸説がありますが、
- 古代、蝦夷防備の狼煙を監視する場所で、狼煙の火を見るところだから火見と言った。
- 海をへだてて、立山連峰の万年雪が見えるところだから氷見と言った。
- 海の漁り火が見えるところだから火見と言った。
- 海が干し上がって、陸地になったところだから干海(ひみ)と読んだ
など、様々な説があります。
市の生い立ち
1871年の廃藩置県後は、金沢藩(旧加賀藩)から金沢県に属しましたが、その後七尾県、新川県、石川県と変わり、1883年に石川県から分離して富山県の一部となりました。1889年には、氷見町ほか20か村が誕生し、1896年には氷見郡となりました。1952年から市制を施行し、その後1954年までに3回の合併を行い、全国でもまれに見る一郡一市となりました。
市の花と木
- 花:ゆり
- 花木:つつじ
- 木:つまま(たぶのき)
姉妹都市
- 長野県大町市
- 静岡県島田市
- 岐阜県関市
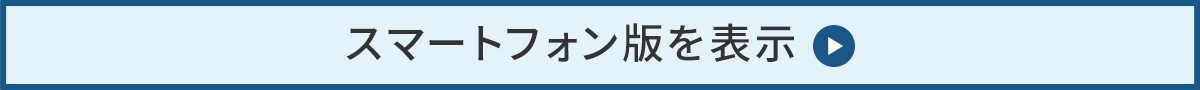








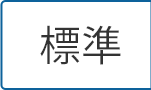




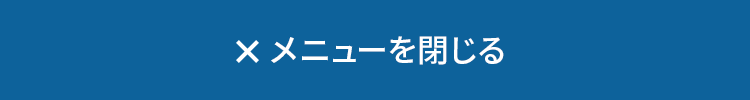
更新日:2020年03月27日