氷見市農業委員会について
ようこそ 氷見市農業委員会ホームページへ
農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項の規定により、市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。
農業者の代表として議会の同意を得て市長が任命した農業委員15人と、地域からの推薦等により農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員19人で構成されています。
農業委員は、総会に出席し、利用権の設定、農地の売買などの権利移動、転用許可など、農業委員会としての意思決定の業務を行います。
推進委員は、各担当地区において、農地利用の集約・集積化、遊休農地の把握・解消、転用許可申請の際の同意書の捺印など、地区に密着した活動を中心に農業委員と連携して現場活動を行います。
農業委員、推進委員の任期は、3年です。
R5農業委員名簿 議席順 (PDFファイル: 128.7KB)
R5推進委員名簿 地区順 (PDFファイル: 121.4KB)
また、事務執行については、「農業委員会事務局」が設置され、農業委員会会長の指揮・監督のもと行われます。
農業委員会の業務
1 農地の売買・貸し借りの許可<農地法第3条>
農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りするには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
権利を取得しようとする者が、農作業に常時従事すると認められない(年間150日未満)場合、耕作放棄地がある場合、周辺農地の営農に支障をきたす場合などは、許可できません。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得を規制し、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
その他、許可基準については法第3条第2項の規定によりますが、詳しくは農業委員会事務局までお問い合せください。
農地法3条許可申請について (PDFファイル: 215.0KB)
農地法3条許可申請用紙(鏡) (Wordファイル: 28.6KB)
農地法3条許可申請用紙(別添) (Wordファイル: 40.7KB)
農地法3条許可申請用紙(記入例) (PDFファイル: 376.1KB)
2 農地転用の許可<農地法第4条・5条>
農地転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地に転用することです。
農地の所有者自らが転用を行う場合には農地法第4条の許可、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合には、農地法第5条の許可が必要です。
許可申請は市の農業委員会が受付し、総会で審議したのち許可相当と判断されれば、意見書を添え県へ進達し、最終的に県知事が許可決定を行います。
無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
農地法第4条許可申請について (PDFファイル: 54.0KB)
農地法第4条許可申請書 (Wordファイル: 81.5KB)
農地法第5条許可申請について (PDFファイル: 66.6KB)
農地法第5条許可申請書 (Wordファイル: 84.0KB)
申請書(別紙1・2) (Excelファイル: 19.4KB)
転用通知書(氷見市土地改良区あて) (Wordファイル: 20.6KB)
転用通知書(西条畑地かんがい土地改良区あて) (Wordファイル: 20.0KB)
転用誓約書(氷見市土地改良区あて) (Wordファイル: 19.5KB)
転用誓約書(西条畑地かんがい土地改良区あて) (Wordファイル: 18.8KB)
地区除外申請書(氷見市土地改良区あて) (Wordファイル: 17.8KB)
・競売買受適格証明書
競売により農地を取得するためには、競売買受適格証明書が必要となります。
証明願は市の農業委員会が受付し、総会で審議したのち許可相当と判断されれば、意見書を添え県へ進達し、最終的に県知事が証明書の発行を行います。
必要な書類は、願出書の他は農地転用(第5条)と同じです。
もし農地転用の許可証を紛失したら…
過去に許可が出ていることの証明書を発行します。
許可証明願に必要事項を記入の上、農業委員会事務局までご提出ください。
3 非農地認定について
非農地認定とは、すでに農地以外の地となっていることが明白である農地で、かつ、要件を満たしている場合に認定をし、通知するものです。
要件については、大きく分けて2つ、自然災害により農地として復旧困難な場合と、耕作されず相当の年月が経過し、農地として復旧困難な場合があります。
この相当の年月については、
・非農業的土地利用がされて20年以上経過していること。
・農業生産力の高い農地で土地改良事業の対象となった農地の場合は、改良事業完了後8年経過した後に、非農業的土地利用がされて20年以上経過していること。
・農業用施設等の補助対象事業の農地内である場合は、補助事業完了後10年を経過した後に、非農業的土地利用がされて20年以上経過していること。
ただし、20年以上経過していることを証明できるもの(建物登記、撮影日の入った写真等)が添付書類として必要になります。
また、20年以上経過している場合であっても、農地法上、違反転用の処分もしくは、農業委員会から違反転用の指導を受けている場合や、農業振興地域整備に関する法律上に基づく氷見市農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地である場合、集団性のある優良農地内である場合は非農地認定をすることが出来ません。
4 農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(農用地の利用権設定)
利用権の設定で安心して農地の貸し借りが行えます。貸借期間等の設定内容は氷見市が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を踏まえた上、貸し手と借り手の間で決めることができます。
利用権の種類には、「賃貸借」と「使用貸借」があり、使用貸借は賃借料が発生しないものです。
利用権には、賃貸借のような法定更新の適用が無いので、貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係は消滅し、確実に貸し手に返還されます。
継続して貸借する場合は「再設定」を行えます。
利用権の設定期間中であっても、止むを得ない場合においては、当事者双方の合意により途中で解約することもできます。
利用権設定等申出書、利用権(設定、移転)関係の書類は、氷見市農林畜産課、氷見市農業委員会事務局、JA氷見市各支所に置いてあります。
★ 「農地中間管理事業」を活用しましょう!(平成25年に制定された新しい事業です)
賃料の受け渡しが口座振り込みにより確実になるほか、固定資産税の軽減措置など、各種メリットが用意されている「農地中間管理事業」制度による農地の貸し借りへの移行をお勧めします。
5 利用権を新たに設定する際など、既存の賃借関係を解約する場合は
農地法第18条第6項合意解約関係書類 (Excelファイル: 63.5KB)
農地法第18条第6項合意解約関係書類(記入例) (PDFファイル: 138.8KB)
6 農業者年金について
農業者年金は、「農業者にもサラリーマン並みの年金を」という強い要望によって、農業者の生活の安定、農業経営者の若返りにより近代化や経営規模の拡大を促進するという2つの目的をもって1971年1月に発足しました。
加入要件
- 20歳以上60歳未満(令和4年5月1日から加入可能年齢が65歳未満へ引き上げ)で国民年金第1号被保険者(免除者を除く)
- 農業従事日数 60日以上
農業者年金には、「経営移譲年金」と「農業者老齢年金」の2つの年金給付があります。(旧制度)
自分名義の農地等を後継者または第三者に貸すか、譲るかして経営移譲した人に経営移譲年金が支給されます。
経営移譲しなかった人には、農業者老齢年金が支給されます。
経営移譲年金は、適格な経営移譲が行われないと、年金受給に至らなかったり、経営移譲後に農地の返還等を受けて農業経営を再開すると、支給が停止されます。
7 定例総会について
農業委員会では、毎月1回(月初め)、定例の総会を開催しています。
農地の売買、貸し借り、農地転用等の申請は毎月15日までに提出してください。
(注意)農用地区域からの除外願、農用地区域への編入願のみ毎月10日までとなっています。
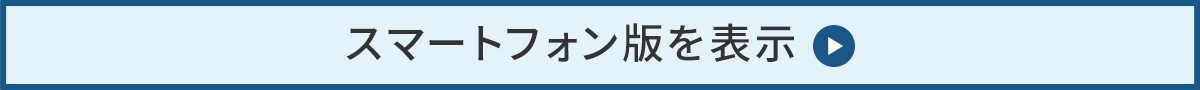








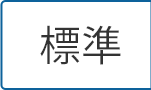




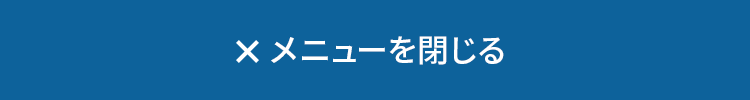
更新日:2023年12月01日