小学校・中学校の就学援助費
概要
小・中・義務教育学校の児童生徒をもつ家庭で、経済的な理由により、お子さんに義務教育を受けさせることが困難な保護者の方々に、学校で必要な学用品費などを援助します。
就学援助は、認定されても学校納金が免除されるものではなく、保護者が学校に支払った費用の一部を、各学期終了後に援助する制度です。
また、現在、就学援助を受給されていても自動的に次年度に継続されません。継続して就学援助を受けたい場合、毎年度の申請が必要です。
援助の内訳
- 学用品費(就学前支給を希望する場合は、 就学援助費の入学前支給のご案内 のページをご覧ください)
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 体育実技用具費
- 医療費
- 学校給食費
申請の手続
援助を希望される方は就学援助認定申請書に、証明書類等を添付し、お子さんが通う学校へ申請してください。
現在、就学援助を受給されていても自動的に次年度に継続されません。継続して就学援助を受けたい場合、毎年度の申請が必要です。
制度の内容や申請の手続については、5月上旬までに、お子さんが通学する学校を通じてご案内します。
申請に必要な書類等
- 就学援助認定申請書(在籍する学校に置いてあります。)(注意)申請書には、スタンプ印は使用しないでください。
- 同意書(もしくは、世帯全員の住民票・所得に関する書類)
- 借家、社宅、公営住宅等にお住まいの方は、領収書又は賃貸契約書のコピー
- 保護者の通帳のコピー
要保護・準要保護児童生徒の認定基準
1 援助の対象となる者
a 要保護
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
b 準要保護者
上記の要保護者に準ずる程度に困窮している者(次の各号のいずれかに該当する者で、保護者世帯(同居者を含む。)の前年の総所得額合計が生活保護基準の1.2倍未満のもの)
- (注意)総所得額とは、所得税法上の合計所得金額に専従者控除額、非課税収入額を足したもの
- (注意)生活保護基準は、前年度12月時点の生活保護基準を適用する。
(1)前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
- ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
- イ 地方税法第295条第1項に基く市町村民税の非課税
- ウ 地方税法第323条に基く市町村民税の減免
- エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
- オ 地方税法第367条に基く固定資産税の減免
- カ 国民年金法第89条及び第90条に基く国民年金の掛金の減免
- キ 国民健康保険法第77条に基く保険料の減免又は徴収金の猶予
- ク 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
- ケ 生活福祉資金による貸付け
(2) 学校長の意見書による者
(収入に関する証明書等が提出できず、かつ、援助の必要があると学校長が判断した場合は、学校長において収入、家庭状況及び学校でかかる費用等の支払状況を調査するものとする。)
保護者の死亡及び離婚等家庭事情の急変した者。なお、前年の収入に関する証明ができない場合は、月収証明を12倍したものをもって前年の収入所得とみなすものとする。
2 認定について
氷見市教育委員会において申請書類を審査し、学校長の同意(確認)を得て、認定を行う。
審査の結果については、学校を通して認定・否認定通知書を保護者に送付する。
3 認定時期
申請が5月から6月の場合:4月1日付けで認定(その後は受付月の翌月認定)
保護者の結婚、他市町村への転出などで認定取消となる場合は、その取消理由が発生した月から認定を取り消すこととする。
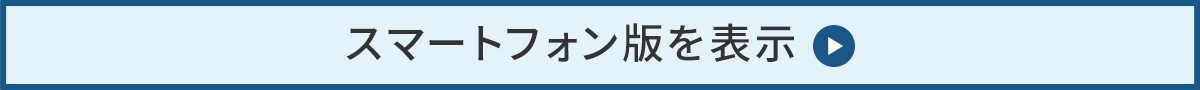








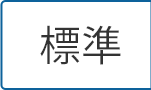




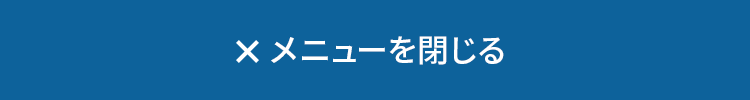
更新日:2024年09月18日