地域活動活性化講座(企画力向上編)の概要
8月4日土曜日に開催された地域活動活性化講座(企画力向上編)
[講師:特定非営利活動法人市民活動サポートセンターとやま 代表理事 能登 貴史氏]の概要は以下のとおりです。
「これから」の時間軸を合わせよう!
地域活動を進めるにあたって、自分たちは「これから」何のために何をしたいのか?
このテーマを話し合う上で必要なことは「これから」の時間軸を参加同士合わせることだと考えています。
その「これから」が来年のことなのか、5年後か、それとも10年後、はたまた30年後?
どの「これから」でも良いが、おすすめは10年後です。
10年後であると年齢とともに、家族や産業構造、そして、地域の環境等の社会システムが大きく変わっていることが想像できます。
その10年後の「これから」を具体的にイメージしてから、何のための何をする「地域活動」を考えていくことが重要です。
社会システムの変化を楽しもう!
ちなみにこれからの環境の変化として、大きく注目されているのが、人工知能(AI)の発達です。
AIは現時点でも日々発達しており、2045年には人類の知能を超えると予想されており、これまで人間が行ってきた仕事をAIが行うようになると予測されます。
このようにこれまでの10年間とこれからの10年後は社会システムが大きく変化することが確実です。
そのような変化を不安と感じ、恐れたままで何もせず過ごすのか、むしろその変化に興味を持って楽しむかはあなた次第だと思います。
今まさに地域づくりのチャンスが到来!
そのような環境の変化の中で、10年後の欲しい環境を作るために今から行動するにあたって、昔と違って今は地域づくりのチャンスが到来していると思います。
なぜなら、行政の仕組みが昔に比べて大きく変わっています。
これまで、行政が中心となって先頭をきってまちづくりをしていましたが、今は各地域がそれぞれありたい姿を実現できるように行政が支援する側に立っています。
また、地方の若い人たちはこれまで学校を出たら首都圏へという傾向でしたが、最近はそのまま地方に留まる、または、首都圏の若い方が地方へ移住することも当たり前の時代になりました。
ITを使って情報を取得しよう!
そして、一番のチャンスがITの進化です。
これまで、ホームページの作成には専門知識が必要で、基本的に事業者に発注することが一般的でしたが、今の時代は自分でしかも無料で作成できます(多少の勉強は必要ですが)。
また、全国の地域活動の事例はインターネットでいくつも検索できることもITの進化によるものです。
これまでは、行政同士の情報共有として冊子にしか載っていなかった事例が、今や誰でもインターネットで検索すればあらゆる情報を取得できる時代になりました。
地域の未来像やビジョンを決めよう!
このようなチャンスのなかで、何かを始めたいが、何から始めたらよいでしょうか?
- 先進事例を真似する
- 組織を作る
- 助成金(補助金)を申請する
- この場所(拠点)を有効活用する
と考える方は多いと思いますが、これらから始めることが正解でしょうか?
私は、まずは、地域の未来像やビジョンを設定することが必要だと考えています。
そして、現状を振り返って、現状と未来像の差が、地域が抱えている課題だと捉えます。
その課題の解決のために、みなさんは組織化し、先進事例を調査し、企画し、資金調達し、活動につなげることになります。
よって、地域活動は先進事例の調査から始まるのではなく、これから」を具体的にイメージすることから始まると私は強く確信しています。
では、「これから」をイメージし、活動するにあたって必要なことは何でしょうか?
私は情報発信等の広報力だと考えております。
広報力については第2回でお話させていただこうと思います。
参加者(アンケート)の声をご紹介します!
- 課題の設定が大事だと思った。
- これまで地域の課題をはっきりと見つけず、企画ばかりに目が向いていた。
- 10年後の未来をわくわくする未来にしたい。
- 見せかけでは活動は続かず、成功もしないと思った。
講座の様子



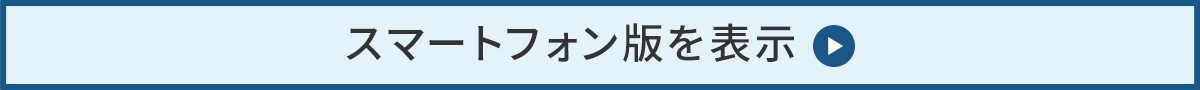








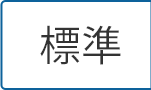




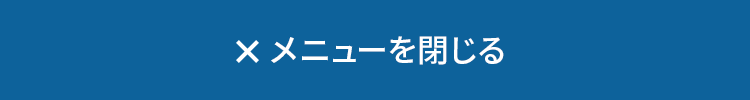
更新日:2020年03月27日