水道事業の概要について
位置と地形
氷見市は、富山県の北西部にあって能登半島の基部に位置し、電源工業地帯の富山平野と能登穀倉邑知潟平野の中間にあって、東は富山湾に面し、北西部は宝達山、石動山、碁石ヶ峰などを主峰とする500メートル内外の丘陵によって石川県と境を接している。 また、宝達山から東南に向かって200メートル内外の二上山丘陵が高岡市と西礪波郡との境界を走り、海老坂峠から急に高くなり二上ブロックとなっている。 これらの丘陵からさらに小丘陵が幾条も派出して、西条・十三・上庄・余川・八代・灘浦の各谷が市街地を中心にして放射状に奥深く刻みこまれ、この谷々を流れる園・神代・仏生寺・上庄・余川・阿尾・宇波・下田の諸川が氷見の穀倉地帯を潤し、石動山から傾斜する地形は、海岸段丘となって灘浦海岸の景観を呈している。
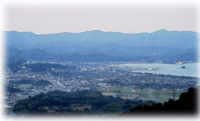
二上山から観る氷見市
沿革
氷見市に水道がひかれる前には、多くの人は飲料水を手掘式浅井戸からの水に頼っていました。これらの井戸の大半は、水質の悪いものでした。 1952年3月に、給水人口30,000人、給水量1日あたり6,000トンの計画により事業認可を得、同年6月に氷見市上水道建設事務所を設置し、市街地を対象として工事に着手、同年12月に一部通水を行いながら1957年2月に事業が完成した。この時の水源は、深井戸の水でした。 井戸水利用の限界と今後の水道普及などが考えられ、1959年度には高岡市が太田地区へ水道を延長した機会に、高岡市から1日当たり1,000トンの分水を受けることになりました。その後も水源の水量不足を補うために、高岡市内を流れる小矢部川の表流水や堀田地区から出る湧水などで、どうにか日量を確保していました。 1979年度から、県営西部水道供給事業に水源を依存し、この結果、水不足になりがちな夏季にも、清浄で豊富な水を得ることが出来るようになりました。

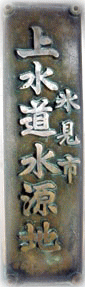
通水式 1952年12月25日 (氷見駅前) 当時の水源地名板
事業の推移
| 区分 計画 | 認可(届出)年月日 | 計画 給水人口 |
1日計画 最大給水量 |
目標年次 | 総事業費 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 創設 | 1951年12月14日 | 30,000人 | 6,000立方メートル | 1954年度 | 154,000 |
| 第1期拡張 | 1959年3月25日 | 30,000人 | 6,000立方メートル | 1959年度 | 9,000 |
| 第2期拡張 | 1962年12月25日 | 50,000人 | 10,000立方メートル | 1973年度 | 1,040,175 |
| 第2期拡張変更 | 1962年12月25日 | 50,000人 | 10,000立方メートル | 1973年度 | 1,040,175 |
| 第3期拡張 | 1974年3月30日 | 55,000人 | 30,000立方メートル | 1985年度 | 2,800,000 |
| 第4期拡張 | 1986年3月25日 | 57,000人 | 25,000立方メートル | 1995年度 | 2,634,820 |
| 第5期拡張 | 1994年3月31日 | 58,000人 | 23,300立方メートル | 2003年度 | 4,829,025 |
| 第5期拡張変更 | 2009年3月31日 | 49,250人 | 21,050立方メートル | 2022年度 | 4,742,900 |
| 第5期拡張変更 | 2012年5月16日 | 48,250人 | 20,130立方メートル | 2022年度 | 3,956,200 |
| 第5期拡張変更 | 2016年3月17日 | 44,100人 | 19,020立方メートル | 2022年度 | 2,387,800 |
| 第5期拡張変更 | 2018年2月23日 | 44,100人 | 19,020立方メートル | 2022年度 | 2,387,800 |
事業規模 (2020年3月末)
| 行政区域内人口 | 46,420人 |
|---|---|
| 給水戸数 | 14,249戸 |
| 給水人口 | 40,349人 |
| 普及率 | 86.93% |
| 送・配水管延長 | 457,396メートル |
| 年間配水量 | 5,468千トン |
| 年間有収水量 | 4,634千トン |
| 1日平均配水量 | 14,939トン |
| 1日最大配水量 | 17,180トン |
| 1人1日平均使用量 | 314リットル |
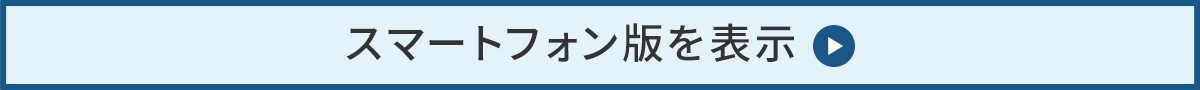








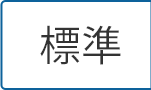




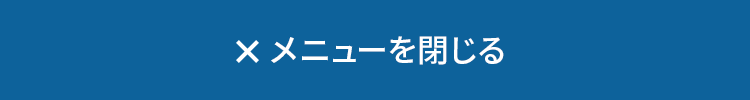
更新日:2020年06月15日