十二町潟オニバス発生地(天然記念物)
かつては野生絶滅したオニバス-絶滅から再生へ-
富山県内では氷見市の十二町潟のみに生息していたが、1979年に記録されて以来、自生地には発生していない(レッドデータブックとやま,2002)とされていたが、潟内の浚渫やガマ刈りの効果もあり、2005年から氷見市の十二町潟での自生が確認されるようになった。潟内の自生数は年々増加しており、2008年には葉の直径が2メートルを超えるもの130株を確認している。
しかし、天然記念物に指定されている十二町潟上流部においては、自生が確認されておらず、地元地区や氷見市オニバス研究会が指定地内でのガマ刈りや移植実験を継続し、指定地内でのオニバス再生にむけて研究を続けている。

オニバスを中心とした緑の浮草が池に生息している写真 拡大画像 (JPEG: 235.5KB)
国指定天然記念物と十二町潟での推移
1923年3月7日
「発生地」が国指定天然記念物となる(富山県初)
- 指定範囲は6178平方メートル 島崎橋から上流へおよそ560メートル
1945年から1955年頃
客土のため、オニバス種子が多く沈む泥を堀りあげる。オニバスは減少。
1968年
万尾川改修工事。指定地内のオニバスに大打撃を与える。
1969年
下流部分(15016平方メートル)が追加指定となる。
1971年10月8日
1923年に指定された範囲が指定解除となる。
1972年から1973年
「十二町潟オニバス発生地の保護育成調査」を実施する。
氷見市立十二町小学校でオニバス池を造成する。
1979年(野生絶滅)
十二町潟から自生のオニバスが見られなくなる。
文献上の記録としては最後の記録となる。
2005年
26年ぶりに十二町潟にてオニバス4株の自生を確認
2006年
十二町潟にてオニバス65株の自生を確認
2007年
十二町潟にてオニバス66株の自生を確認
2008年
十二町潟にて葉の直径が2メートルを越えるオニバスを130株確認
(注意)しかし、十二町潟の上流部である「十二町潟オニバス発生地」において自生は確認されていない。
その他の情報

オニバスの葉の上で紫色の花が咲いている写真 拡大画像 (JPEG: 90.3KB)
指定年月日:1923年3月7日
所在地:氷見市十二町中開4322番地(実測15,016平方メートル)
(注意)「十二町潟オニバス発生地」のパンフレットは希望の方に郵送します。
希望される方は教育総務課へメールを送信
8月上旬頃から十二町潟水郷公園内でオニバスの花が観察できます。
この記事に関するお問い合わせ先
博物館
郵便番号:935-0016
富山県氷見市本町4番9号 氷見市教育文化センター1階
電話番号:0766-74-8231 ファックス番号:0766-30-7188
メールでのお問い合わせはこちら
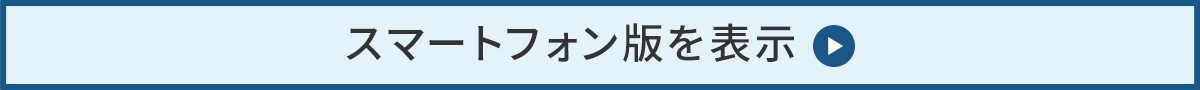








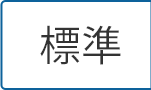




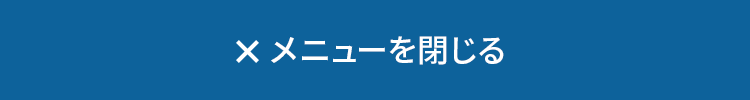
更新日:2020年03月27日